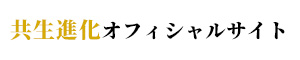| 開催日 | 2025年3月19日 |
| ゲスト | 野中ともよさん |
| コメンテーター | 稲本 正 |
今回はゲストに野中ともよさんを迎え、SDGsの“その先”を見据えた世界観の転換、そして教育と文化をどう変えていくかについて語り合いました。
キーワードは「全体を見る力」と「命は“生きている”のではなく“生かされている”」という感覚です。30分という枠の中で、危機感と希望の両方が濃く詰まった回になりました。
2030年は“ゴール”ではなく、分岐点です
稲本さんが最初に語ったのは、2030年のSDGs達成に対する強い危機感でした。残り時間が少ない中で、いちばん怖いのは「どうせ無理だ」と人々が諦め始めることだと言います。
だからこそ必要なのは、2030年で話を終わらせず、その先まで見通した視点を持つこと。
「まだ行ける」と信じた上で、未来を組み立て直す時代に入っている—そんな問題提起から対話が始まりました。
スペシャリストだけでは、世界がバラバラになります
続いて話題は「全体を見る力」へ。
稲本さんは、専門家(スペシャリスト)の重要性を認めつつも、専門が細分化されすぎると社会全体が“バラバラ”になり、トータルでつなぎ直せる人がいなくなると語りました。
そして、その“つなぐ力”を育てる場が教育である、と。
専門を深めるだけでなく、全体像を見渡し、橋をかけられる人を育てなければならない。これは今の時代に不可欠なテーマです。
野中ともよさんが語る「国際人」ではなく「地球人」
ここで野中さんが提示したのが、「全体性」の捉え直しです。
結論はシンプルで、「私たちはみんな地球の上で生きている」という一点に集約されるというのです。
野中さんは「国際人」という言葉があまり好きではないと話します。国際人という言葉には、どこか“英語ができて海外経験がある人”という狭いイメージが混じることがある。
その代わりに野中さんが大切にしたい言葉が「地球人」です。
地球人なら、どこで何をしている人でも名乗れる。
そして「地球は今どうなっているのか」を見ようとする視点そのものが、全体性につながっていく——この考え方が、今回の軸になっていました。
まだ分かっていないことだらけの地球で、私たちは“上”に立ってしまった
対話はさらに大きなスケールへ広がります。
宇宙の理解が進み、ミクロな粒子の世界と宇宙の始まりがつながって見えてきた一方で、分からないことは圧倒的に多い。ウイルスも、森も、川も、海も、山も、そして地球そのものも、まだ十分には分かっていない。
それなのに人間は、まるで自分たちが自然から切り離された“上位”の存在になったかのような錯覚を抱き始めたのではないか。
中村桂子さんの議論にも通じるこの感覚が、ここで改めて強く語られました。
自然を「支配する対象」にした発想は、戦争ともつながっています
野中さんは、ヨーロッパ的な世界観として「自然を見下ろし、退治し、開拓する」という発想を取り上げました。
森は怖く暗いものだから切り開くべきであり、自然は人間に奉仕すべきものだ——こうした考え方が“文明”の名のもとに進んできた。
その延長線上に、戦争と自然破壊の接続がある、という指摘も出ます。
敵を見通すために森を伐り、道を切り開く。ジャングルを裸にする。
自然を「制圧すべき対象」と見る視線は、人間同士の暴力にもつながっていくのだ、という話は重く響きました。
コロナ禍が見せた「2週間で水が澄む」という現実
印象的だったのは、コロナ禍のベネチアの例です。
外出や移動が止まり、飛行機も車も減った。たった2週間で、水が澄んだ。
つまり私たちの暮らし方が、環境と直結していることは、理屈ではなく現象として“見えてしまった”わけです。
ところが社会はすぐに「経済を戻さなければ」と元通りの生活へ回帰し、いまに至っている。
では、何に気づかなければいけないのか。
その答えは「今まで通りの便利さや経済合理性だけで走れば、結局また元に戻る」という一点にある——野中さんのメッセージは明快でした。
「いただきます」に宿る、“生かされている”という感覚
ここから話は、「謙虚さ」と「文化」へつながります。
野中さんが強調したのは、水や太陽や雲、自然の恵みに対する畏敬と感謝を取り戻すことでした。
その象徴が「いただきます」です。
これは“自分に言っている言葉”ではなく、自然や命への感謝の言葉。海外でその意味を説明したとき、強く感動されたというエピソードも紹介されました。
さらに野中さんは、祖母から繰り返し教わった言葉を語ります。
魚だけでなく、トマトにも、米一粒にも命がある。
そしてそれらが「あなたの命になるために来てくれている」。だから「命をいただきます」と言いなさい——この教えが、野中さんの人生観の土台になっているのです。
ここで提示されたのが、
「生きている」のではなく「生かされている」
という感覚でした。
教育は“制度批判”だけでは間に合いません
教育の話題では、稲本さんが制度の硬直性を痛感してきた経験を語ります。
教科書、仕組み、現場の余裕のなさ——変えるのが難しい現実がある。
ただ、だからといって「文科省が悪い」「先生が悪い」と言っている暇はない。
野中さんは、子どもは地球の宝物であり、受験や学歴、いい会社のための教育だけでは意味がないと気づいた大人が、地域や家庭から伝えていく必要があると語りました。
制度を責めるより、まず“気づいた側”が動く。
時間が残されていない今、そこが出発点になるのだと思います。
自然の中の“想定外”が、感性を育てます
稲本さんは、子ども時代の自然体験がいかに決定的かを、自身の家族のエピソードも交えて話しました。
木を植える、動物と暮らす、森のそばで育つ。そこでは想定外の出来事が普通に起こり、その驚きが人の感性を育てる。
生命の本質は循環と変化であり、変化しないことの方がむしろ危険だ—この感覚を、教育の中で失ってはいけない。そんな強いメッセージが残りました。
次回はインドの話へ
最後に稲本さんから次回の案内がありました。
インドの話、そして企業と人間の関係なども含めて、もう一度「世界」と「全体」から考える回になるとのことです。