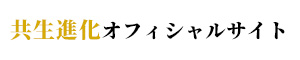| 開催日 | 2025年5月4日 |
| ゲスト | 田中優子さん |
| コメンテーター | 稲本 正 |
5月4日の「共生進化ネット」は江戸時代のものづくりと自然観を深掘りする回となりました。
冒頭から提示されたのは、私たちが抱きがちな「江戸=遅れていた」という思い込みを、根本から問い直す視点でした。
結論から言えば、江戸は“遅れていた”どころか、循環・教育・技術・都市設計をセットで回していた、かなり先進的な社会だったのです。
宇宙で多いものを、江戸はちゃんと大事にしていた
稲本さんがまず持ち出したのは、意外にも「宇宙の元素の話」でした。
宇宙で圧倒的に多い元素は水素。次いでヘリウム、そして酸素。
水素と酸素が多いということは、水が多いということでもあります。地球の表面は2/3以上が水で覆われていますが、地球以外にも水がある可能性は高い。近年は火星の水の存在も話題になりますが、稲本さんは「論理的に考えれば、調べなくても“あるべき”ものだ」と語ります。
さらに、水素の次に多いのが炭素。
炭素と水素を基盤にした物質は、植物や動物、そして私たちの体を形づくるタンパク質や炭水化物につながります。
ここから稲本さんが導いた整理が面白い。
江戸は、水と、炭素・水素を基盤とする“生命の循環”を大切にしていた。
宇宙で多い順番のものを、ちゃんと大事にしていた社会だった。
この発想を土台に、田中さんが江戸のものづくりの話へ入っていきます。
平和の250年が生んだ「工夫の爆発」
田中さんは、江戸時代が約250年以上にわたり大きな戦争のない時代だったことを確認します。
平和が続いたからこそ、生活の改良や技術の蓄積が進み、ものづくりが発展した。
一方、江戸以前の日本は、国内で作るよりも、鉱物資源などを対価に中国の優れた製品を買うことが多かった。ところが、外から買い続けるほど国内で作る力は育ちにくい。田中さんはその構造を指摘しつつ、戦乱や海外侵略(秀吉の朝鮮出兵)による疲弊を経て、江戸が「ゼロから作り直す時代」になったと語ります。
江戸城周辺の造成が湿地の整備から始まった、という話も象徴的でした。
“都市も社会も、作り直す”——その覚悟が江戸にはありました。
家康がやった最強の投資:印刷=教育=国家の土台
田中さんが「家康はすごかった」と評価したのが、活字印刷への注目でした。
活字は明治に突然登場したわけではなく、江戸直前から現れていた。それに家康が強い関心を持ち、こう考えたというのです。
- 活字があれば教科書が作れる
- 教科書があれば武士を教育できる
- 教育が整えば国の基盤ができる
- そして知識がものづくりを押し上げる
結果として江戸では、本づくりと学びの仕組みが広がります。寺子屋が増え、教科書が流通し、識字率が高くなる。
「読む人」がいるから本が生まれ、本があるから学びが広がり、学びがあるから技術が育つ—この循環が、江戸の強さでした。
江戸は閉じていない。外から学び、内で“作れるようにした”
田中さんが繰り返し強調したのは、江戸が「鎖国で止まっていた時代」ではないという点です。
中国やインド、さらにヨーロッパ由来の技術や機械類も入ってくる。そこで江戸の人々はこう考える。
これ、どうやれば自分たちで作れるだろう?
その結果、レンズ、和ガラス、鉄砲、時計など、さまざまなものが国内で作られるようになります。
外から来たものをただ消費するのではなく、理解し、工夫し、自前化する。江戸のものづくりは、まさに「吸収と再構成」の文化でした。
基本は“里山”—生活の80%を支えた循環システム
ただし江戸の土台は、最先端技術だけではありません。
田中さんが「基本」として挙げたのは里山でした。
里山は共有地で、草を刈って肥料にし、キノコや山菜を採り、炭や燃料の木を得る。
農民が人口の大部分を占める時代に、里山は生活そのものを支える「循環の装置」だったのです。
稲本さんはここから現代への問題提起もしました。
かつて山と人の境界には犬がいて、熊や猪を遠ざける役割を果たしていた。しかし犬がペット化していくことで、山の秩序が変わり、獣害が増える。
里山の話は、そのまま今の暮らしの話につながっていきます。
江戸の大都市を可能にしたのは「水インフラ」だった
江戸の都市としての成立を支えたのは、水の設計です。
玉川上水のような長距離の導水によって、江戸の生活用水を確保する。しかも水は、町だけでなく農地にも分配され、周辺の土地を豊かにします。
田中さんは、この仕組みが中村哲さんのアフガニスタンでの灌漑事業と通じる点にも触れました。
大きな機械が持ち込めず、壊れても直せない環境では、現地の人が維持できる技術が必要になる。その意味で江戸の土木技術は、現代の「持続可能性」にも直結します。
さらに江戸の町には水路が張り巡らされ、物流にも人の移動にも使われていました。水が流れる都市は熱がこもりにくく、真夏でも過度に暑くなりにくい。
江戸の“快適さ”も、水の設計が作っていたのです。
時計が使えない国が、時計を作った—和時計とからくり
技術の話で特に面白かったのが「和時計」です。
ヨーロッパの時計は一定の時間を刻みますが、日本の時刻は日の出から日没までを6等分する不定時法。季節で昼夜の長さが変わるため、普通の時計では合いません。
ところが日本は、ここで諦めなかった。
重りを調整し、歯車の動きを微妙に変え、季節に合わせて進み方が変わる時計を作ってしまった。
これが和時計です。
この技術は、からくり人形にもつながり、さらに舞台装置(競り上がり、回り舞台など)へ発展します。
「歯車の理解」が、娯楽の進化まで連れていったのが江戸のすごさです。
焼き物、和ガラス、眼鏡、そして“遊び心”
江戸は輸出品も作ります。陶磁器は中国の影響を受けつつ、日本独自の意匠を確立し、海外で模倣されるほど評価されました。
また和ガラスも発達し、後の切子につながる洗練された作品が生まれます。田中さんは「職人の力は技能だけでなく、センスがある」と語りました。
さらに面白いのが眼鏡。江戸には眼鏡屋が複数あり、普及した結果、眼鏡をネタにした戯作まで登場します。
「眼鏡をかけたら相撲が見える、富士山が見える、友達が見える」—まるでテレビのような発想。
技術が生活に入り、さらに“笑い”や“想像力”へ転化していくのが、江戸らしさです。
綿は魚で増えた:干鰯が支えた衣の革命
衣の分野では綿が画期的でした。
インドや中国、朝鮮半島では作られていたのに、日本は長らく輸入に頼っていた。ところが江戸に入って綿栽培が急速に広がります。
鍵になったのは肥料、特に干鰯(イワシを発酵・乾燥させた肥料)です。
魚は食べるだけでなく、農業を支える資源でもあった。
綿が増えれば織りと染めが進み、インドの更紗に刺激を受けて、日本の職人が模倣から新しいデザインを生み出していく。縞模様が江戸で大流行したのもこの流れです。
そして最後の衝撃:「鎖国」という言葉は江戸の外から来た
終盤、田中さんは「鎖国」という言葉の成立を説明します。
ケンペルが来日し、帰国後に書いた『日本誌』が1801年に翻訳され、その際「鎖国論」と呼ばれたことで、日本に「鎖国」という語が入ってきた。
重要なのは、江戸に「鎖国令」という法令がないこと。
ケンペルの趣旨は「日本には国内に十分な資源と技術があり、輸入に頼らなくても成り立つ」という観察でした。
「閉じた国」という単純なレッテルではなく、自給と技術の充実として見られていた、ということです。
稲本さんはここから、「小さな自給圏を日本にたくさん作ることが、戦争のない社会につながる」という未来像を語り、田中さんも「それは江戸が実現していた社会像だ」と応じました。
まとめ:江戸は“懐かしい過去”じゃない。未来の設計図だった
今回の対談で見えてきた江戸は、こういう時代でした。
- 平和の中で技術と工夫が積み上がった
- 印刷と教育が、ものづくりの土台になった
- 海外から学び、国内で作れる形に再構成した
- 里山と水の循環が生活を支えた
- 和時計やからくりに象徴される高度な機構技術があった
- 「鎖国」という言葉は後から入ってきた概念だった
江戸は「遅れていた時代」ではなく、
循環と学びで社会を回し続けた“持続可能なものづくり文明”だったのかもしれません。