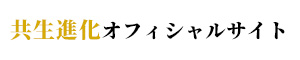| 開催日 | 2025年8月10日 |
| ゲスト | 枝廣淳子さん |
| コメンテーター | 稲本 正 |
今回は30分という時間を確保し、枝廣淳子さんとじっくりお話をする回となりました。
枝廣さんといえば、多くの方がまず思い浮かべるのは、レスター・ブラウンやアル・ゴアの著作翻訳を通じて、日本に環境問題を伝えてきた存在ではないでしょうか。
しかし今回の対談では、その「翻訳者」という肩書きの奥にある、より個人的で、より身体感覚に近い話が次々と浮かび上がってきました。
レスター・ブラウンとの出会いは「自分から行った」ことが始まり
枝廣さんが環境問題に関わるようになった原点は、レスター・ブラウンとの出会いにあります。
当時、環境問題に強い関心を持ち、レスター・ブラウンの『地球白書』を読み込んでいた枝廣さんは、英語を話せること、通訳の仕事をしていたことを活かし、「自分が本当に大切だと思うテーマで通訳をしたい」と考えるようになりました。
そこで枝廣さんが取った行動は、非常にシンプルなものでした。
日本に来るとき、ホテルの送り迎えだけでもいいので、通訳をさせてください。
枝廣さんは、自らレスター・ブラウンに連絡を取ったのです。
その結果、日本側のパートナーから連絡が入り、実際にホテルと会場の送迎時の通訳を担当することになります。
最初は、会議通訳でも何でもない、いわば“入口”の役割でした。
しかし、レスター・ブラウンと移動中にさまざまな話を重ねるうちに、少しずつ信頼関係が築かれていきました。そして次第に、記者会見や同時通訳まで任されるようになっていきます。
このエピソードからは、「世界は意外と、きちんと連絡をすれば応答してくれる」という感覚が伝わってきます。
『不都合な真実』の翻訳は、ほぼ不可能なスケジュール
レスター・ブラウンとの仕事をきっかけに、枝廣さんは環境分野の通訳・翻訳者として知られるようになります。
その延長線上で巡ってきたのが、アル・ゴアの『不都合な真実』翻訳の話でした。
その条件は、非常に厳しいものでした。
- アル・ゴアの来日に合わせて出版すること
- 翻訳期間は約1か月
- その1か月のうち、丸1日作業できる日は4日しかない
通常であれば断っても不思議ではない状況ですが、枝廣さんは「やります」と引き受けます。
そこで用いられたのが、通訳者ならではの技術でした。
英語の原文を見ながら、日本語でそのまま読み上げて録音し、それを文字起こしして翻訳の叩き台にするという方法です。
これは「サイトトランスレーション」と呼ばれる手法です。
文章として書こうとすると、人はどうしても「もっと良い表現はないか」と立ち止まってしまいます。しかし、話すことで一気に流れを作ることができます。また、日本語入力で止まりがちな漢字変換のロスもありません。
極限まで集中して翻訳作業を続けるうちに、不思議な感覚が生まれたといいます。
文章を見ていると、アル・ゴアの声が、日本語で聞こえてくるようになったのです。
翻訳とは単なる言葉の置き換えではなく、「その人になりきること」なのだと、強く感じさせられるエピソードでした。
「良い翻訳だ」と言われた一言の重み
来日したアル・ゴアに、翻訳者として挨拶した際のことです。
自分は日本語が読めないから内容は分からないけれど、日本人の友人たちが「とても良い翻訳だ」と言っていました。
この一言は、枝廣さんにとって非常に大きな意味を持つものでした。
翻訳の良し悪しは、原著者本人ではなく、その言語で読む読者が決めるものです。
だからこそ「本人になりきる」ことが、結果的に読者に届く翻訳につながるのだといいます。
対談では、ノーベル賞と翻訳の関係、文学作品と翻訳の話題にも広がり、「伝わるかどうか」が何よりも重要だという認識が何度も共有されました。
温暖化は「未来の話」ではなく、すでに起きている
『不都合な真実』は、世界中に大きな影響を与えました。
水位上昇を階段ではしごを使って示すなど、誰にでも分かるプレゼンテーションは、気候変動を一気に「自分ごと」にしました。
しかし枝廣さんは、いま改めて強い危機感を抱いています。
温暖化は「100年後に起こるかもしれない話」ではありません。
すでに猛暑、水害、森林火災といった形で、現実の問題として表れています。
それにもかかわらず、日本では切迫感がまだ弱いと感じているそうです。
海外では市民レベルでの行動が進んでいる一方で、日本では「一部の人が頑張っている」状態にとどまっているのが現状です。
その背景には、教育や政治、情報の伝え方、そして「成長は永遠に続く」「時間は無限にある」という無意識の前提があるのではないか、という指摘もありました。
「伝える」だけでは足りなくなった理由
枝廣さんが手がけた翻訳書は50冊以上、自身の著作も50冊近くにのぼります。
それでもなお、「言葉で伝えること」だけでは限界があると感じるようになったといいます。
そこで、活動の軸足は「現場で変化を起こす」方向へと移っていきました。
10年以上にわたり地方創生の現場に関わり、全国各地のまちづくりを支援してきましたが、あくまで外部からの応援という立場でした。
次第に、「自分自身が現場のプレイヤーになりたい」という思いが強くなっていったのです。
なぜ熱海だったのか
もともと海が好きだった枝廣さんは、海を見ながら仕事ができる場所として熱海に惹かれていきました。
最初は週末拠点として、海が見える部屋を購入します。
そしてコロナ禍をきっかけに、神奈川の住まいを引き払い、熱海へ完全に移住しました。
東京から近く、これまで通り仕事も続けられる。
それでいて、自然があり、変化が目に見える場所でもあります。
地域に根を張ることは、匿名性がなくなり、煩わしさも増えます。しかしその代わり、海藻が一本増えた、炭が固定されたといった「確かな手応え」が得られます。
小学生時代に刻まれた「持続可能性」の感覚
枝廣さんが「持続可能性」という考え方を体で理解したのは、小学校1年生の頃でした。
宮城県の山奥で育ち、自然の中で遊ぶことが日常だったそうです。
ある日、両親のために山菜を取ろうとして、枝ごと折ってしまった結果、翌年はもう生えてこなかったといいます。
取りすぎなければ続いたのに、元を断ってしまったら終わってしまった。
この体験は、「元本に手をつけず、利子だけを使う」という持続可能性の原理として、枝廣さんの中に深く刻まれました。
モデルをつくり、広げていくという考え方
現在、熱海では藻場再生や炭化といった取り組みを「モデル」として確立し、それを全国へ広げていくことを目指しています。
重要なのは、個人だけで完結させないことです。
行政、漁師、企業、地域住民など、多様な立場の人が関われるプラットフォームをつくることが鍵になります。
一つの成功例が生まれれば、人は動きやすくなります。
だからこそ、まずは一つの場所で「うまくいく形」を現場でつくることが大切なのです。
次回へ
今回の対談で浮かび上がったのは、
言葉で伝える力と、現場で引き受ける覚悟を両立させる姿勢でした。
次回は『農業が温暖化を解決する』を起点に、
農業、食、そして次の社会のあり方について、さらに深く掘り下げていきます。