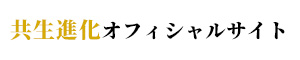| 開催日 | 2025年11月1日 |
| ゲスト | 林 英哲さん |
| 司会 | 原田 伸介 |
| コメンテーター | 稲本 正 |
日本の太鼓を“現代芸術”へ。林英哲が語る、創造と挑戦の55年【インタビュー前編】
世界的な太鼓奏者・林英哲さんに、共生進化ネット稲本が話を伺いました。
今回は“前編”として、英哲さんがどのように日本の太鼓を再構築し、世界へ羽ばたいていったのか、その原点を深く掘り下げていきます。
運命の再会──2000年ハノーバー国際博から始まった縁
実は英哲さんと我々の出会いは20年以上前に遡ります。
2000年のハノーバー国際博覧会にて、現地で演奏をご一緒し、ドイツの観客が息をのむほど集中し、割れんばかりの拍手を送ったあの光景は今でも鮮明に記憶しています。
今日は、その英哲さんが日頃鍛錬を重ねる“秘密の道場”にお邪魔し、改めて「林英哲とは何者か?」を伺いました。
「日本の太鼓を音楽にする」──誰もやっていなかった挑戦
林英哲さんが太鼓を始めたのは約55年前。
当時は今のように「〇〇太鼓」と呼ばれるジャンルは存在せず、太鼓はあくまで“祭り・宗教儀礼・合図”などで使われる道具であり、音楽として扱われるものではありませんでした。
「伝統芸能を学びながら、そこに現代的な表現を加える。
太鼓を“舞台芸術”として成立させることが僕の出発点でした。」
衣装、セッティング、打ち方、ステージ運び――
そのすべてを自分で考え、「日本の太鼓を音楽として成立させる」という、当時誰も試みていなかった挑戦が始まります。
「どんな状況でも演じろ」──若き日の修行と無茶ぶり
独立後、地域活動家のAさんからの声掛けがきっかけで、数々の“荒行”にも挑戦することになります。
たとえば、太鼓を叩きながら火起こしをし、火がついたら花火を上げるという前代未聞の企画。
昼はすぐ火が着いたものの、湿気の多い夜はまったく火がつかず、1時間以上叩き続ける羽目に。
「観客は楽しんだと思うけど、僕はもうヘトヘトでした(笑)」
また打ち上げの席では「コップで何か演奏しろ」と突然の指令が飛ぶことも。
この“どんな状況でもパフォーマンスを見せろ”という教えが、英哲さんを鍛え上げていったのです。
ドラム少年が太鼓奏者へ─ビートルズとの出会い
中学生の頃、英哲さんはビートルズに衝撃を受け、ドラムから音楽の世界へ飛び込みます。
英語の歌が難しいため、当時流行していた「ベンチャーズ」のコピーを友人たちと演奏するなど、音楽少年としての青春時代を過ごしました。
しかし、ドラムの技術が太鼓に“邪魔”をする場面があると言います。
「ドラムは手首で軽く叩くけど、太鼓は全身で“疲れるように”叩く。
ドラムが上手すぎると太鼓には向かないんです。」
結果的に“完璧ではないドラムの腕前”が、太鼓への自然な移行を助けたのだとか。
修行は稽古より“走り込み”!?
海外で戦うための体力づくり
英哲さんが所属した当時のグループは、とにかく“体力至上主義”。
太鼓の稽古よりも、朝4時からの日体大式の走り込みが中心でした。
「海外で戦うには体力が必要だと言われて、とにかく走りました。」
この体力は後に「ボストンマラソンを完走してから太鼓を叩く」という企画につながり、アメリカでも大反響を呼びました。
手順を分析し、譜面化し、ユニゾン化──太鼓に“作曲”を持ち込んだ革命
当時、太鼓に作曲法は存在しませんでした。
お祭りの林はアドリブで受け継がれる世界で、型があるわけではなかったのです。
そこで英哲さんは、演奏を録音し、それを譜面化。
手順を固定化し、複数人で揃えて打つ「ユニゾン」へと再構築します。
これにより、太鼓は初めて「舞台で魅せる表現」になりました。
ただし…
「地元からは『伝統を勝手に変えた』と相当恨まれました。」
この経験から、以降は伝統の原型があるものに手を加えず、すべて自作曲で勝負するようになっていきます。
世界へ羽ばたく太鼓表現へ(後編へつづく)
英哲さんの創造と挑戦は、やがて国内外の大舞台へとつながり、
金閣寺での演奏や、ベルリン・ワルトビューネなど世界的ステージへ広がっていきます。
その歩みの続きは【後編】で詳しく紹介します。
「太鼓を“総合芸術”として形づくる」
林英哲という表現者の原点に迫るインタビュー、次回もぜひご覧ください。