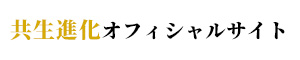| 開催日 | 2026年2月01日 |
| ゲスト | 日比野克彦さん |
| コメンテーター | 稲本 正 |
私たちは、なぜアートを生み出してきたのでしょうか。
そして、なぜ今の社会では「すぐ役に立つもの」ばかりが求められているのでしょうか。
今回の共生進化ネットでは、アーティストであり東京藝術大学に関わる日比野克彦さんをゲストに迎え、アートと社会、人間の創造性の根源について語っていただきました。本記事では、その対談内容をもとに、現代におけるアートの意味をあらためて考えてみます。
東京藝術大学は「社会の役に立つ大学」であるべき
東京藝術大学(藝大)は、音楽学部と美術学部を持つ、日本で最も歴史ある芸術大学のひとつです。今年で創立138年を迎えました。
一般的に藝大というと、「倍率が高い」「卒業後が大変」というイメージを持たれがちです。確かに厳しい世界であることは否定できません。しかし日比野さんは、そうした見方だけでは不十分だと語ります。
もし身近な若者が「藝大に行きたい」と言ったとき、「大変だからやめておけ」と言うのではなく、「それは社会の役に立つ道だ」と応援できる社会にしたい。
藝大は、トップクリエイターを育成するだけでなく、社会的課題に芸術で向き合う人材を育てる場であるべきだと考えているそうです。
そのため現在は、「すぐに役立つかどうか」では測れない、根源的な価値を探る研究や教育にも力を入れています。
芸術は、人間が人間であるための営み
人類は何万年も前から、踊り、描き、歌ってきました。
芸術は、学問よりも前に存在していた人間の営みです。
見えないものを理解したい、恐怖を形にしたい、祈りを捧げたい。
そうした衝動から、人は像を作り、模様を刻み、物語を生み出してきました。
たとえば縄文時代の漆塗りの櫛は、完成までに半年近くかかると言われています。石の道具だけで素材を採取し、削り、仕上げる。それは当時の人々にとって、最先端の技術でした。
芸術は装飾ではなく、機能を持ち、信仰や生活と密接に結びついていたのです。
暗闇と空腹が、人間の感覚を呼び覚ます
日比野さんは、電気のない夜を体験したことがあると言います。
夜は驚くほど暇になり、自然と星を眺める時間が生まれます。
エジプトの砂漠でテント生活をしながら星を見続けた夜。
目を閉じても星の残像が消えず、やがて流れ星まで見えてくる。
暗闇の中では、人間の感覚が研ぎ澄まされ、世界の見え方が変わってくるのです。
アマゾンの奥地では、川の中央でエンジンを止め、空と水面に映る星を同時に眺めたこともあったそうです。
上にも下にも広がる宇宙を前に、「地球は宇宙の一部にすぎない」と身体で理解できた瞬間でした。
こうした体験は、日常生活ではなかなか得られません。
「結果だけ」を求める社会が、創造性を奪う
現代は、時間や手間をかけずに結果だけを得られる時代です。
疑似体験やシミュレーションも簡単にできます。
しかし、砂漠へ向かう長い移動時間や、食べ物がなく空腹に耐える時間があってこそ、その体験は深く心に刻まれます。
プロセスを省略してしまえば、感覚も記憶も薄れてしまうのです。
日比野さんは、こう語ります。
「結果だけが評価される社会では、いずれすべてをAIに任せることになる」
創造性は、効率やコストパフォーマンスの外側にあります。
空腹は、最大の調味料である
アマゾンでは、数日間ほとんど食べ物がなく、コーヒーとナッツ菓子だけで過ごしたこともあったそうです。
その後、ようやく手に入った硬い肉は、人生で一番おいしく感じたと言います。
「空腹は最大の調味料だ」という言葉がありますが、それは単なる比喩ではありません。
価値や喜びは、そこに至るまでの過程があってこそ生まれるのです。
これは食べ物に限らず、学びや創作、人生そのものにも当てはまります。
アートは、人間を人間に戻すためにある
効率化が進み、結果だけが重視される時代だからこそ、
遠回りをし、待ち、感じることの価値を、アートは思い出させてくれます。
芸術は、すぐに役立たなくてもいい。
しかし、人間が人間であり続けるために、確実に必要なものです。
次回は、日比野克彦さんが東京藝術大学で担っている役割や、教育の現場で何を考えているのかについて、さらに深く伺っていきます。