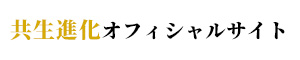| 開催日 | 2026年2月08日 |
| ゲスト | 日比野克彦さん |
| コメンテーター | 稲本 正 |
前回は「食」から話が広がりましたが、今回は改めて「アートとは何か」「表現の原点はどこにあるのか」というテーマに深く踏み込んでいきます。
本記事では、日比野さんの幼少期の記憶、高校・大学時代の経験、そして表現と社会との関係についての語りを、流れを保ちながら整理してご紹介します。
岐阜という原風景と、絵を描き始めた理由
日比野さんは岐阜県立加納高校の出身です。
当時から美術や音楽に力を入れている少し変わった高校で、全国的に見ても芸術系へ進む生徒が多い環境でした。
しかし、日比野さんが「絵を描く理由」を本格的に意識するようになったのは、ずっと後になってからだと言います。
その原点を辿ると、岐阜市を流れる長良川の風景、そして川に架かる橋の存在に行き着きます。
特に幼少期、日常的に渡っていた「忠節橋」は、アーチ型のシルエットも含めて強く印象に残っており、後に作品のモチーフとして何度も登場します。
20代後半から30代にかけて、自分の制作のルーツを振り返る中で、「岐阜の風景が自分の中に深く刻まれている」ことを、あらためて自覚していったそうです。
「好きな色」は、子どもの頃に決まっている
日比野さんは、色鉛筆の話を通して「感覚の記憶」について語ります。
数百色ある色鉛筆の中で、なぜか特定の赤だけが極端に減っていく。他の色と見た目は大差ないのに、その色だと手が自然に動く。
理由が分からないまま時間が経ち、ある日、実家で幼少期に遊んでいた積み木を目にした瞬間、気づきます。
その赤色が、自分の好きな色鉛筆とほぼ同じ色だったのです。
身近で安心できた色の記憶が、「好き」「落ち着く」という感覚として身体に残っていた。
日比野さんはこれを、絶対音感になぞらえて「絶対色感」とも言えるものではないかと語ります。
色に限らず、味覚やバランス感覚など、人の感性は幼少期の環境の中で育まれていく。
この話は、表現が決して後天的な技術だけではないことを示しています。
「自分は一人だ」と知った瞬間の風景
話題は、さらに深い幼少期の記憶へと進みます。
日比野さんが覚えているのは、幼稚園の頃、家に帰ると誰もいなかった日のことです。
親や友達が戻ってくるのを見渡せる場所として、川に架かる小さな橋の上で、ひとり川の流れを見ながら待っていた記憶。
それは決して大事件ではありません。
しかし、「自分は一人の存在なのだ」「自分以外の他者がいる」ということを、初めて強く意識した瞬間だったのかもしれないと日比野さんは振り返ります。
この「他者の存在を知ること」こそが、表現の出発点だと言います。
自分とは違う誰かがいるからこそ、「伝えたい」「分かり合いたい」という欲求が生まれ、表現へと向かうのです。
ダンボールに描き始めた理由
東京藝術大学に進学した日比野さんは、45人のクラスの中で制作に打ち込みます。
周囲には、それぞれ得意分野を持つ仲間がいて、「立体がうまい人」「描写が鋭い人」など、他人の個性はよく見える一方で、自分自身の「らしさ」はなかなか分かりません。
そんな中、友人や教員から言われたのが、「完成作品より、ラフスケッチの方が日比野らしい」という言葉でした。
本人としては、きちんと仕上げた作品こそが本番のつもりだったため、大きな戸惑いがあったと言います。
しかし、楽しく自然に手が動くのはラフの方だった。
その延長線上で、きれいな画材ではなく、段ボールという素材に描くようになり、それが現在につながる表現のスタイルの出発点となりました。
自分らしさに気づかせてくれたのは、常に「他者」だった。
この点が、日比野さんの語りの中で何度も強調されます。
藝大で一番大切だったもの
日比野さんが振り返って「藝大で一番大切だった」と語るのは、設備やカリキュラム以上に、同世代の仲間の存在です。
同じ時代、同じ関心を持つ人たちと、制作のプロセスを共有する。
東京藝術大学では「作品は教室で制作する」という方針があり、家に持ち帰って仕上げた作品は認められません。
これは、完成形ではなく、途中の試行錯誤や手順こそが学びだからです。
誰がどんな色を混ぜ、どのタイミングで筆を置くのか。
そのすべてが、教室という場で共有されていました。
社会とつながるアート、そして学長という役割
話は、日比野さんが学長に就任した背景へと移ります。
学長は立候補制ではなく、推薦と選考によって決まりますが、日比野さん自身は、これまで一貫して「社会とアートをつなぐ活動」を続けてきました。
ポスターや広告、プロダクト、街づくり、地域連携。
アートを美術館の中だけで完結させず、社会の中に開いていく試みです。
SDGsや環境問題、地域コミュニティが重視される現代において、大学にも外へ向かう姿勢が求められるようになりました。
その流れの中で、美術学部長として「福祉と芸術」をテーマにした取り組みを進め、結果として大学全体を担う立場へとつながっていきます。
一人ひとりの「らしさ」から、未来は生まれる
今回の対話を通して浮かび上がるのは、
表現とは「特別な才能」ではなく、幼い頃の記憶や感覚、他者との関係の中で育まれていくものだという視点です。
平均化が進む時代だからこそ、平均化できない感覚や記憶が、創造性の源になる。
日比野克彦さんの言葉は、そのことを静かに、しかし力強く示していました。
次回は、さらに「社会との関係性」に焦点を当てて話が続きます。
ぜひ引き続き、ご覧ください。