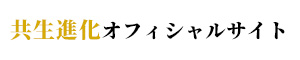| 開催日 | 2025年1月5日 |
| ゲスト | 太刀川英輔さん |
| コメンテーター | 稲本 正 |
今回はゲストに太刀川英輔さんをお迎えし、対談をお届けします。
これまでの回では、自然と人間社会の中で「どこに目を向け、どう捉え直すべきか」を中心に話してきました。今回はそこから一歩進めて、未来や次世代へどうつなぐかという視点で深掘りしていきます。
未来に役立つデザインだけをつくる、という覚悟
稲本さんが投げかけたのは、「未来のために、今どんなことができるのか」という問いでした。
それに対し太刀川さんは、ご自身の活動をこう語ります。
太刀川さんは「未来に役立つデザインばかりをすることがライフミッション」だと位置づけ、防災、脱炭素、食、地域、衛生、集合地、教育など、さまざまな分野で具体的にどんなデザインが可能かをまとめたケーススタディ集を制作したと言います。
未来を語るとき、理想論だけでは届きません。
現場で使える形に落とし込んだ「実例」があるからこそ、次の一歩が踏み出せます。
気候変動対策は「緩和」と「適応」に分かれる
今回の対談で中心となったのが、太刀川さんが取り組む「アダプトメント」というプロジェクトです。
ここで重要なのが、気候変動への対応が大きく2つに分かれるという整理です。
- 緩和策:CO₂など温室効果ガスを減らす。再生可能エネルギーを増やす。
- 適応策:気候が変わる前提で、災害・暑さ・農業・暮らし方を「変化後の世界」に合わせる。
緩和策は「CO₂を下げる」という目標が明確なため、資金も集まりやすく、取り組みも進みやすい面があります。
一方で適応策は、日傘をさすことから都市設計まで、何でも含まれてしまうほど範囲が広く、全体像がつかみにくい。その結果、社会の中で重要性が理解されにくく、進みにくいという課題があるのです。
「適応策」を進めるには、まず“構造”が必要です
太刀川さんは、適応策が進まない理由をこう捉えます。
「適応策の全体像が理解されていないからではないか」
そこで太刀川さんが着想したのが、生物の“適応進化”から学ぶというアプローチでした。
都市や暮らし方を「どう適応させるか」を、生物の適応進化の視点から構造化し、わかりやすい枠組みにしていく。東京大学や国立環境研究所などの専門家と議論を重ね、その枠組みを作り上げたと言います。
さらにこの枠組みは、日本国内だけでなく、インドネシアやフィリピンといった災害の最前線でも共有され、プロジェクトとして動き始めています。
ここが印象的なのは、実装していくほど「最先端技術」よりも、むしろ昔はできていたのに今できていないことが重要になってくる、という気づきです。
「自給遊園」―忘れられた暮らしの知恵を取り戻す
ここで話題は、稲本さんが長年取り組んできた実践へとつながります。
稲本さんが語るのは「自給遊園」という考え方です。
自給しながら、遊びながら、しかし本気で暮らしを組み立てる。木を育てるには時間がかかる。100年かかるものは100年かかる——そんな時間感覚をもった暮らしです。
そして稲本さんは、かつて日本の農村が当たり前のように行っていた「自給に近い暮らし」が、戦後のある時期まで確かに存在していたことも振り返ります。
壊してしまったものを、もう一度思い出し、地域を作り直す。そこに未来へのヒントがあるのではないか、という問題提起です。
世界にもある「もう一つの暮らし方」のモデル
稲本さんは、日本だけでなく海外にも似た構造があると指摘します。
たとえばロシアには「ダーチャ」という文化があります。
週末に郊外の土地へ行き、畑や小さな家を持ち、生活の一部を自分たちで成り立たせる。社会の歪みや不安が高まるほど、そうした「生き延びるための小さな楽園」が現実的な選択肢として立ち上がってくるのです。
またアメリカでは大恐慌の時代、失業者を地方へ送り、農業や林業に従事させて生活を成り立たせる政策もありました。
生き延びるための仕組みづくりは、時代が変わっても繰り返されます。
そして、ここにこそ「デザイン」が関わる余地がある、と話は深まっていきます。
街づくりは「3つのスケール」で考えると見えてくる
太刀川さんが提示した整理が非常に明快でした。
街をつくるには、スケールを3つに分けて考えるべきだというのです。
- マスタープラン(土地利用計画・全体設計)
- ハードウェア(建築・土木・インフラ)
- ソフトウェア(コミュニティ・文化・教育)
この3層を「生物の適応進化から学ぶ」と、最初に立ち返るべきものとして浮かび上がってくるのが——流域です。
「流域単位」に戻すことが、適応の第一歩です
雨が降ったとき、水はどこへ流れるのか。
その水の流れの単位が「流域」です。
太刀川さんは、街のマスタープランを考えるうえで、この流域単位に戻すことが重要だと述べます。なぜなら流域は、ハザードマップとも一致し、防災の基礎単位になるからです。
昔の地名には、水や地形の特徴が刻まれていました。
しかし現代の住所や区割りは、流域の単位と切り離されてしまっています。
流域単位で設計し直すことは、防災だけでなく、農業や自然回復、生態系保全ともつながる。
この基礎を無視すると、土砂災害のような被害につながりかねない。そんな警鐘でもありました。
レジリエンスは「頑丈さ」だけで成立しません
次に話題は、ハードウェア=都市の強さへ移ります。
太刀川さんは、生物の体を例に出しながら、こう説明します。
生物は「頑丈だから生き延びる」のではなく、
柔軟性、循環、バッファー、回復など複数の仕組みで支えられています。
その構造を都市に当てはめるなら、レジリエンスには例えば次のような性質が必要になります。
- 危険を察知できる(覚知性)
- 元に戻れる(回復性)
- 代替がある(冗長性)
- うまく循環する(循環性)
- しなやかに受け止める(弾力性)
- 壊れにくい(頑強性)
水害なら調整池のような冗長性、棚田のような“受け止める構造”、グリーンインフラのような緩衝。
それらは実は「昔はあった知恵」でもある、という視点が印象に残ります。
防災を決めるのは「コミュニティと伝承」です
最後に焦点となったのが、ソフトウェア=コミュニティです。
太刀川さんは、防災の現場で「人と人のつながり」がいかに重要かを語ります。
危ないとき、協力できる関係があるか。
顔が見える関係があるか。
そして、災害の知恵が伝承されているか。
お祭りや地域の行事には、つながりを保ち、知恵を継承する役割がありました。
「津波が来たら神社へ逃げなさい」という教訓が残っていた地域では、実際に避難行動が変わります。
神社がぎりぎり安全な場所に建てられていた例が多いのも、場所の記憶が積み重なった結果です。
街は、インフラだけでは守れません。
文化や関係性も含めて、レジリエンスが決まるのだと感じさせられました。
次回は最終回へ―次世代につなぐために
今回は「適応策」の全体像を、生物から学ぶ視点で構造化し、街づくりをマスタープラン/ハード/ソフトの3層で捉え直す話が中心でした。
そして何より、「昔できていたことを取り戻す」ことが、最先端の適応にもつながるという示唆が強く残りました。