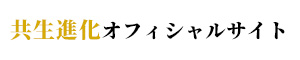今回は、長年にわたり世界中で太鼓や芸能活動を続けてきた林さんが、芸術や文化、人との出会いを通して感じてきた「国境を超える力」についてお話します。日本や韓国、フランス、アフリカなど多様な地域で得た経験を、対談から抜粋しブログ記事として読みやすく再構成しました。
ソローの思想に触れたことから始まった“テーマとの共鳴”
林さんは若い頃から世界を旅し、社会運動や市民思想に触れてきました。特に『市民の反抗』というソローの書籍に影響を受け、その思想はのちの創作にも自然と滲んでいます。
今回、マン・レイさんという人物をテーマに作品を作ることになり、そこからさらに学びを深めました。それは偶然の一致というより、同じテーマが同時に自分の前に現れる“シンクロニシティ”のようなものでした。
弟子が増えたことを機に、彼の中にある美術的な視点をより明確に形へ落とし込む必要を感じ、マン・レイさんの表現を音で再構築するという挑戦が始まりました。
美術出身の感性が導いた「マン・レイ」との出会い
林さんは元々美術の出身ということもあり、「石を吊るす」「竹を響かせる」といった視覚的な要素と太鼓を組み合わせた作品を作りました。弟子たちが活躍できる構成に仕上げたところ、非常に好評をいただいたそうです。
ソロも魅力がありますが、複数で取り組むからこそ生まれる“掛け合いの面白さ”があり、若い奏者が頑張る姿、揃った音の迫力。それらが作品全体を新しい次元に押し上げてくれると語ります。
伊藤若冲との邂逅──密画の経験が導いた新たなテーマ
マン‣レイをテーマにした後、次に出会ったのが伊藤若冲でした。
ボタニカルアート(密画)を学んでいたため、若冲の緻密な描写には特別な衝撃を受けたといいます。
当時、若冲はまだ世間ではほとんど知られていません。
読み方さえ「これ何と読むの?」と聞かれるほどで、一般公開もほぼない時代でした。
しかし実際の作品を目の前にすると、誰もが驚きます。
「どうしてこれが知られてこなかったのか?」と思うほどの完成度です。
その後、若冲の再評価ブームが起こったのは必然だったのでしょう。
若冲の「音が聴こえるような迫力」に惹かれた林さんは、それを太鼓で表現する作品を制作しました。
浅川巧さん──名も無き“橋渡し役”の生涯
そしてもう一人、深く心を動かされた人物がいます。
それが、朝鮮半島で林務職員として働いていた日本人・浅川さんです。
彼は荒れた土地に松を植え続け、100年後には立派な森林となりました。
向こうの人々が日本に連絡し、育てた松を日本へ送りたいと言ってくるほど大切にされていました。
さらに、恵まれない子どもたちの学費を自費で支援し、後に陶芸の人間国宝へと成長する人物も生まれました。
民芸運動を始めた柳宗悦が朝鮮の工芸に光を当てる際、その最前線で文化資料を収集していたのもこの浅川さんだったのです。
林さんはこの人物をテーマに太鼓作品を制作し、日韓文化交流の一環としてソウル国立劇場で初演しました。文化が政治の分断を越える瞬間を、まさに目の当たりにした経験だったと語っています。
藤田嗣治に感じた“同じ苦悩”
フランスで活躍した藤田嗣治(レオナール・フジタ)。
彼は独自の“乳白色の肌”を描く絵で世界的評価を受けましたが、日本・フランスの両方から相反する批判に苦しみ続けました。
- 日本では「フランス人の真似をするな」
- フランスでは「なぜ日本的な絵を書くのか」
その“文化の狭間の苦しみ”に、林さんは強い共感を覚えます。
太鼓も日本では過小評価され、海外では高く評価される。
その落差に何度も心が揺れました。
パリで初めて藤田さんの実物を見た時、印刷物とは比べ物にならない迫力に圧倒されました。芸術の本質は“生”でこそ伝わると実感した瞬間です。
アフリカで出会った「言葉を超えるコミュニケーション」
アフリカにも何度も訪れましたが、特に驚いたのが トーキングドラム(会話できる太鼓) だったと言います。
音の抑揚だけで意味が変わり、日本語の「橋」と「箸」のように太鼓の音で会話が成立します。
林さんが現地で習いながら打つと、村の子どもたちが意味を理解して合唱する場面がありました。
しかし、技術が不十分だと反応はありません。
この差に、太鼓の文化的な奥深さを強く感じたそうです。
また、木彫り職人が林さんのノミの扱い方を見て一瞬で「職人だ」と理解する場面もありました。
言葉が通じなくても技術が通じる。
これは文化交流の最も純粋な形ではないでしょうか。
STOMPとの交流──文化は巡り、再びつながる
イギリスのパフォーマンス集団STOMPが、林さんの道場に太鼓を習いに来たことがあります。
彼らは和太鼓の演奏を見て「自分たちは別の素材で挑戦しよう」と決め、ゴミバケツやほうきなどを使った独自スタイルを作り上げました。
道場での稽古は大喜びで、記念に道具を置いていってくれましたそうです。
文化は伝わり、変化し、巡り、また別の形で戻ってくる。
その象徴のような出来事でした。
文化は言葉以上に人をつなぐ
結局のところ、
「世界を変えよう」という言葉より、
“文化を通した自然な共感”の方がずっと強い力を持つ
と林さんは感じています。
太鼓もアートも工芸も、
国を超え、時代を超え、人々の心をつないでいます。
彼は70歳を過ぎた今でも活動を続けています。
かつては「70で引退しよう」と思っていたそうですが、新しい発見や繋がりはむしろ増えているようで、今後は教育の現場にも文化の視点を広く届けたいとお考えであり、林さんの活動はこれからも続きます。
これからも文化を通して、人と人が共感し、共生し、進化していく未来をつくっていきたい。
そう語るのでした。