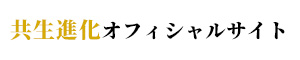| 開催日 | 2025年5月11日 |
| ゲスト | 田中優子さん |
| コメンテーター | 稲本 正 |
「昔、浅草の“太田さん”がよく“にわか”って言ってたんだよね。でも当時は何のことか全然わからなかった。」
5月11日の「共生進化ネット」は、そんな稲本さんの個人的な記憶から始まりました。ところが話は、やがて吉原の大イベント「にわか」へとつながり、蔦屋重三郎の出版活動、歌麿の大首絵、そして俳諧の革命へと広がっていきます。
今回の回が面白いのは、江戸文化が「過去の知識」ではなく、記憶・暮らし・循環として現代に立ち上がってくるところです。
102歳まで生きた母の記憶、そして“わからない父”
稲本さんは、まず家族の話をします。
母親は102歳まで生き、驚くほど記憶力が良かった。調べていくと、家のことがどんどんわかっていった。一方で、父親の来歴は不明な点が多く、「親が誰なのかさえよくわからない部分がある」と言います。
学生時代、稲本さんは文化系で、小説家志望でもあり、「とにかく東京へ出たかった」。
その時、父親に「浅草の太田さんのところへ行け」と言われ、よくわからないまま訪ねてみた。
そこで出会った太田さんは、面白いけれど何を言っているのかよくわからない。
「にわか」とか言っていたが、当時は意味がつかめなかった。
でも、後年。本を読んで初めて腑に落ちた。
「あ、太田さんが言ってた“にわか”って、これのことか」
記憶は、知識によって突然つながる。
江戸の話が、急に“自分の話”になった瞬間でした。
吉原の「にわか」は、1か月毎日続く“町ぐるみの芸能祭”だった
田中さんは、「にわか」が吉原で行われた大きな祭りだったことを説明します。
踊り、楽器の演奏などを披露しながら、中の町の茶屋を一軒一軒まわって見せていく。
しかも規模がすごい。
- 旧暦8月1日から1か月間
- 雨が降らなければ、ほぼ毎日
1日だけの祭りではなく、1か月間“興行が続く街”だったわけです。
稲本さんが「すごいな……」と唸るのも当然です。
そして重要なポイントがもう一つ。
ここで主役になるのは遊女ではなく、芸者だということ。
「にわか」で鍛えられた吉原芸者は、日本でも一流の芸者へ育っていく。
吉原は遊女と芸者という“別の生き方”が同居し、その両方が文化を作っていた——田中さんはそう整理します。
見物は“誰でもできた”。吉原は閉じた場所で、開いていた
「これ、誰でも見に行けたの?」という稲本さんの問いに、田中さんは「見られます」と答えます。
道筋で眺めることができる。
花火の季節などには多くの人が入り、店に上がらない人でも外から見物していた。
吉原は閉じた世界として語られがちですが、行事の時には町の“外側”と接続する。
つまり江戸の娯楽は、排他的というより、意外なほど“開かれている瞬間”を持っていたのです。
桜並木は“自然”ではなく“演出”だった:江戸の季節は突然出現する
話題は桜へ。
江戸の桜は、今のように「そこにずっとある風景」ではなく、植木屋が一気に運び込み、通りの真ん中にずらっと並べて“桜の波”を作った、という話が出ます。
つまり桜並木は、いわば舞台装置。
稲本さんは、現代のイベントでも「咲いた状態で持ってきて、終わったら撤去する」ような運用があることを挙げ、「江戸も同じことをやってたんだ」と驚きます。
正月、盆、季節の行事……。
江戸の町は年中、芝居のように“季節を演出”し続けていた。
それを見に来る人がいて、また次の行事が始まる。ここにも循環がありました。
遊女たちは“日本文化ほぼ全部盛り”の教養を持っていた
田中さんは、吉原の女性たちが身につけていた教養にも触れます。
琴、笛、踊り、茶の湯、香道。
俳諧や漢詩ができる人もいた。
まさに日本文化全般を体得している人がいた、という話です。
「小紫」という名が紫式部に由来し、代々受け継がれていた例も紹介されます。
写真の残る時代の小紫は凛としていて、日々の鍛錬が伝わってくる——。
芸能は“才能”だけでなく、生活の中で鍛えられていくもの。
江戸の文化の強度は、こうした日常の積み重ねに支えられていました。
蔦屋重三郎:吉原専門の版元から、江戸の文化エンジンへ
ここから話は、蔦屋重三郎へ。
田中さんは、蔦屋が最初「吉原の版元」だった点を明確にします。
当時、吉原専門で出版する版元はほとんどいなかった。蔦屋はそこで、吉原や遊女に関する出版を次々に手がけ、やがて日本橋へ移り、扱う範囲を広げていきます。
その中で大きな存在になったのが、喜多川歌麿でした。
歌麿の「大首絵」は、引き出しで“会う”ための絵だった
蔦屋が取り締まりを受け、店を一時的に閉じざるを得なくなった後。
再起をかけて始めたのが、歌麿の「大首絵」だったという話が出ます。
胸から上だけを大胆に描き、背景を省く。
すると髪の毛一本一本、肌の微妙な色合いまで見えてくる。
ここで田中さんが語る、江戸の鑑賞スタイルが面白い。
江戸の人は浮世絵を壁に飾らない。
引き出しにしまっておき、手元で取り出して見る。
目の前に人がいるみたいになる。
だから大首絵は、その“見方”にふさわしい。
つまりこれは、展示用の絵ではなく、**“会うための絵”**だったということです。
俳諧は世界を反転させる:「蛙鳴く」じゃなく「蛙飛びこむ」
終盤、稲本さんは俳諧の話へ移ります。
松尾芭蕉とニュートンがほぼ同年代であることを引き合いに出しつつ、芭蕉の言葉の革新を語ります。
和歌の世界では「蛙(かわず)」には型があり、「かわず鳴く」が定番だった。
ところが芭蕉は「鳴く」ではなく「飛びこむ」を置いた。
「かわず鳴く」ではなく「かわず飛びこむ」
型を破り、世界を反転させる。
その一撃で、別世界が立ち上がる。
稲本さんは、蔦屋重三郎が吉原から始まり、やがて学術的な領域にまで接続する出版へ伸びていく姿にも、同じ“飛躍”を感じているようでした。
まとめ:新しいものは突然生まれない。循環が生む
今回の対談を貫いていたのは、「循環」という感覚でした。
- 記憶が知識でつながる循環
- 年中行事が町を動かす循環
- 芸が鍛錬で育つ循環
- 出版が文化を広げる循環
- 和歌→狂歌→俳諧→川柳と受け継がれる循環
新しいものは、突然現れるわけではない。
過去をよく見て、使えるものを引き継ぎ、作り変えながら生まれてくる。
だから江戸を学ぶことは、懐古ではなく、いまの社会のバランスを取り戻すヒントになる——。
そんな余韻を残して、今回の回は締めくくられました。
次回予告
次回(5月18日)は「江戸と循環」がテーマ。今回は15分でしたが、次回は30分でより深く扱います。