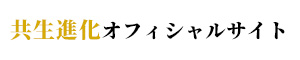| 開催日 | 2025年4月06日 |
| ゲスト | 山極壽一さん |
| コメンテーター | 稲本 正 |
「家族進化論」を読んで、もう一段深く聞きたくなった
共生進化ネットの4月6日回。
稲本さんは、山極壽一さんの著書『家族進化論』を読み込み、「次はもっと突っ込んで聞きたい」と切り出します。
現場で見ないと分からないことがある。
聞くのと見るのではまるで違う。
その実感を持つ稲本さんの言葉に、山極さんは「今日は家族というテーマに寄り添って話します」と応じ、家族研究の歴史から語り始めました。
そもそも「家族」はいつから学問になったのか?
家族が学問の世界で大きく扱われ始めたのは19世紀。
ダーウィンが進化論を発表し、1871年の『人間の由来』で「人間も他の生物と同じように進化してきた」と示します。これが哲学者や社会学者、文化人類学者の関心を刺激しました。
その代表がルイス・モルガン。
彼は『古代社会』で、人間社会も古代から進化してきたはずだと考え、欧米以外(アジア・南米・アフリカなど)の社会を調べ、家族形態を比較します。そして「ヨーロッパ型こそ進んだ形で、他は古い形を残している」と論じました。
しかし、ここに強烈な反発が起こります。
「人間は同じような時間を経て進化してきたのだから、家族の一部だけで“進んでいる・遅れている”と評価してはいけない」
文化相対主義の台頭により、家族を“進化”で語る研究は一気に慎重になっていきました。
ただし、家族が人間にとって根本的な社会組織である以上、「家族の成り立ちを知りたい」という欲求自体は消えませんでした。
流れを変えたのは「霊長類を比べる」という発想
そこで登場するのが今西錦司さんです。
今西さんは生物の社会や歴史を論じ、家族を重要テーマとして捉えました。
モルガンが“現代の人間社会”だけを横並びで比べたのに対し、今西さんの発想はこうです。
- 霊長類には多様な種がいる
- それぞれが進化の歴史を持っている
- 共通点は祖先から受け継いだ特徴
- 違いは分岐後に発達した特徴
ならば霊長類を比較すれば、「家族の原型」が見えるのではないか。
当時、ゴリラの社会はほとんど分かっていませんでしたが、「人間の家族に近いらしい」とされ、“類家族”という言葉まで与えられます。調査は1958年に始まるものの、独立紛争で中断。そこから1967年にダイアン・フォッシーが人づけを進め、ゴリラの姿が少しずつ明らかになっていきました。
そして、家族の問題に関心を持ち、ゴリラ研究を担う人間が必要になった。
そのとき伊谷純一郎さんに声をかけられたのが、山極さんでした。
「家族って結局なんだ?」という違和感が、ずっと残っていた
山極さんが家族に強い関心を持った背景には、高校紛争の体験があります。
社会を変えるために熱く議論しても、人は最後に家族のもとへ帰っていく。
その光景を見て、「家族とは何なのか」「なぜそこへ戻るのか」が気になり続けた。
本を読んでも腑に落ちない。
だからこそ霊長類研究に出会ったとき、「猿を研究することは、人間の過去を研究することになるかもしれない」と感じた―この流れが、ゴリラ研究へと繋がっていきます。
ゴリラは“怪物”ではなく、むしろ争いを避ける
キングコングなどの影響で、「ゴリラ=凶暴」という誤解は長く広がってきました。
1856年にヨーロッパ人によって「発見」されると、探検家の宣伝も相まって、野獣のように語られ、捕獲され、動物園に送られました。
その結果、ゴリラは不幸になり、動物園で100年以上繁殖すらできなかった。
しかし研究が進むにつれ、ゴリラはむしろ争いを避ける平和的な動物だと分かっていきます。
ただ、本当に理解するには「群れの内側」に入らなければならない。
山極さんは現地で許可を取り、村人や森の民(ピグミー)の人々と関係を築き、言葉を覚え、森を歩き、ついにはゴリラの群れの中に座り込みます。
「周り全部ゴリラ」という状況で、ゴリラを緊張させないように、ゴリラのように動き、ゴリラの声も出しながら、自然な行動を記録し続けました。
家族は「父親が成立することで」生まれる
ここで山極さんは、核心に触れます。
多くの哺乳類では、社会の中心は「母と子」です。
オスは交尾のために一時的に現れて去ることが多い。
ところが霊長類には、オスとメスが継続的に共に暮らす例があり、ゴリラはその代表格です。
しかし、家族が成立する鍵は単に“一緒にいること”ではありません。
父親が成立すること
これが家族の出発点だというのです。
しかも父親は「自分が父親だと自覚したら成立」ではない。
メスに選ばれ、さらに子どもから“親だ”と認められて初めて成立する。
父親とは、メスと子どもの二重の選択を経て作られる存在。
ここが非常に人間的でもあります。
シルバーバックが子どもに教える「安心」と「公平」
ゴリラ社会では、成熟したオス「シルバーバック」が子どもの安全基地になります。
子どもは母親から少しずつ離れていき、不安になる。
でもシルバーバックの周りには年上の子どもが集まっていて、遊びの輪に入ることで安心していく。
シルバーバックは、子どもが飛びついても基本的に動じません。
体格差があるからこそ、恐怖を与えないよう“動かない”という配慮をする。
そしてトラブルが起きると、即座に仲裁します。
面白いのは仲裁の仕方です。
「特定の子だけを助ける」のではなく、喧嘩を仕掛けた側、あるいは力の強い側を抑える。
結果として、子どもたちは「喧嘩は悪い」「誰かが特別扱いされているわけではない」と学びます。
母親は自分の子を特別に守りやすい。
でも父親は、群れ全体の子どもを見なければならない。
その立場が、より公平な“裁き”を可能にしているのです。
人間の家族の原型はどこにあるのか?
ここから話は人類進化へと広がります。
チンパンジーは人間に近いと言われるのに、家族の原型が見えにくい。
乱婚的で、父親が特定されず、子育てはメスが担う社会だからです。
では人間の家族の原型はどこにあったのか。
この問いはまだ100%解けていない。
ただ、化石から分かる手がかりの一つが「男女の体格差」です。
初期人類はゴリラほど極端ではないが、現代人よりは差が大きい。
そこからゴリラに近い社会を想像できる可能性もある。
山極さんの仮説では、森林を出てサバンナで暮らすようになり、危険が増したことで防衛のための大きな集団が必要になった。血縁集団同士が関係を復活させ、協力し合い、外敵から家族を守る形へと進んだのではないか。という見立てです。
「人間の家族」は、共同体を含んで初めて成立する
そして最も印象的だったのが、この定義です。
一組の夫婦だけでは「人間の家族」とは呼べない。
複数の家族が集まり、共同体ができて初めて成立する。
なぜなら、家族だけでは子育てが成立しないから。
サバンナで生き残るためには出産頻度を上げる必要があり、早期離乳が必要になる。すると離乳した子を誰かが育てなければならず、「共同保育」が不可欠になる。
つまり共同体は、子育ての単位として生まれた。
現代の狩猟採集民を見ても、家族と複数家族からなる共同体が基本単位になっている。これは世界的に見ても非常に古い形だ――山極さんはそう語ります。
農耕が生んだ「定住」と「所有」が、争いを加速させた
後半では、人類が農耕へ移行した後に起きた変化が語られます。
食料生産は大転換点であり、定住と所有を生んだ。
蓄えができ、再分配が可能になり、人口が増える。
人口が増えれば土地が必要になり、良い土地の奪い合いが起きる。
作物を守るために武力が必要になり、集団間抗争が始まる。
ただし、農耕が始まってから文明が成立するまでには長い時間がかかっている。
農耕は必ずしも健康や幸福をもたらす制度ではなかった。
それでも移行が起きた背景には、「所有」が人間の欲求を大きく満たした側面がある――この視点は、現代にも刺さります。
いま必要なのは「切り分けず、全体で捉える」視点
環境問題や戦争の問題は、部分に分けて理解するだけでは解けない。
物事をトータルに見る視点を取り戻さなければならない。
次回(4月13日)では、その後半として「人類がどう生きるべきか」という問いをさらに掘り下げていきます。