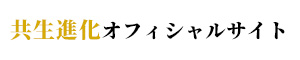| 開催日 | 2025年2月9日 |
| ゲスト | 隈研吾さん |
| コメンテーター | 稲本 正 |
今回のテーマは、隈さんの著書『自然な建築』。前回までの「負ける建築」や来歴の話を踏まえつつ、隈さんが考える“自然”の定義が、どのように建築へ落とし込まれていくのかが語られました。
『自然な建築』は、隈研吾の「裏側」が見える本
稲本さんは冒頭、『自然な建築』を読んでみて「仕事の裏側、つまり何をどう苦労して形にしてきたのかが見える」と感じたと語ります。
そして、近代建築の流れ(ミース・ファン・デル・ローエなど)を踏まえたうえで、隈さんが独自のスタイルを確立しつつあった時期に、この思想が結晶化したのではないか、と問いかけました。
ライトの「自然な建築」と、今の「自然な建築」は違う
隈さんは、「自然な建築」という言葉自体は昔からあると前置きします。たとえば20世紀初頭の建築家フランク・ロイド・ライトも“自然な建築”を語っていました。
ただしライトの自然観は、葉っぱの形のような「自然に似た形」を建築に取り込むことや、緑を建物と一体化させることなど、比較的「形」や「演出」に寄った自然の捉え方だったといいます。落水荘のように、滝の上に建築を張り出し、石を室内に残すなど、自然の迫力を“建築の中に持ち込む”発想です。
もちろん、当時誰も「自然な建築」を言い出さなかった時代にライトがそれを語ったことには大きな意味があります。
しかし、隈さんは「今の時代に必要な自然の捉え方は、そことは違うのではないか」と考えるようになった、と語りました。
自然は“外”ではなく“素材の中”にもある
隈さんが提示する新しい自然観の核心はここです。
自然は「外にある野生を建築に持ち込む」だけではなく、素材の中にも自然が宿るという考え方です。
竹、和紙、石。素材を深く掘り下げていくと、その素材が生まれ、加工され、使われ、循環していくプロセスそのものに“自然”が含まれている。
そして建築が、その循環の一部になれたとき、建築は自然と対立するものではなく、自然のシステムの中に組み込まれる──隈さんは、そうした状態を「自然な建築」と呼びたいのだと話します。
稲本さんも、縄文時代の竪穴住居の例を挙げながら、地面を掘ることで夏涼しく冬暖かいという合理性があり、建築が自然と一体だったことを補足し、隈さんの思想に共感を示しました。
「庭の石だけ」で挑んだ、石のミュージアム
話題は、思想が実際の作品へどう結びつくかに移ります。
隈さんが紹介したのは、栃木県那須の小さな石屋さんとの出会いです。庭を掘って出てくる石を扱いながら、「石のミュージアムを作りたい」という夢を持っていた。しかし資金も潤沢ではなく、使える石は基本的に“庭の石”だけでした。
隈さんは、その制約をむしろ思想として引き受け、庭の石と職人の技だけで作品を成立させる挑戦をします。
「豪華な素材を集めてミュージアムを作る」のではなく、「そこにある素材だけで、どう建築を立ち上げるか」。この姿勢が、まさに“循環の一部としての建築”につながっているように感じます。
万里の長城のそばで「竹の建築」を作るという挑発
さらに隈さんは、中国でのプロジェクトを語ります。
万里の長城の頂上付近という場所での建設計画に手を挙げたものの、現地に行ってみると、給排水やインフラの段取りすら検討されていない、経験の浅いデベロッパーだったといいます。
当時の中国は高層建築が急増し、自然が壊されていく時代でした。隈さんは、そうした状況に対する“批評”として、違う価値観を提示する建築を作ってやろうと考えます。
そこで選んだのが、中国で足場材として大量に使われている竹でした。
図面通りじゃない竹が、むしろ「優しさ」を生んだ
竹で恒久的な建築を作ることには、現地側も最初は抵抗があったそうです。
しかし隈さんは、日本の竹研究の知見や職人のノウハウ(竹を長持ちさせる処理など)を持ち込み、竹の建築を成立させていきます。
現場ではトラブルもありました。
隈さんは竹経験のあるインドネシア人留学生を現場に常駐させていましたが、ある日その留学生から「大変です」と電話が入ります。図面では直径も間隔も揃えてあるのに、運び込まれた竹は太さも違えば曲がってもいる。「これでは建築になりません」という訴えです。
ところが隈さんは現場で実物を見て、逆にこう感じます。
不均一で曲がった竹が、硬さのない“優しい表情”を生むかもしれない。
結果として、完成した建築はランダムな動きと柔らかさをまとい、独特の魅力として高く評価されました。
北京五輪へ─竹の家が「中国を象徴する映像」になった
そしてここから、事態は大きく動きます。
北京オリンピック前、映像ディレクター(映画監督)から「竹の建築を、中国を象徴する映像として使いたい」という話が来たのです。当時は日中関係が悪化していた時期で、日本人建築家の作品が五輪の公式映像で扱われるのは異例でした。
隈さんが了承すると、実際に開会式でも大きく映像が流れ、中国中に広まりました。さらに日本でも広告で取り上げられたタイミングが重なり、竹の建築は一気に注目を集めます。
その結果、「あの建築家に頼みたい」という依頼が増え、隈さんの中国での活動が拡大する大きな転機になったと語られました。
隈事務所は“多拠点ラボ”で動く
対談終盤では、隈さんの事務所のスタイルにも話が及びます。
東京だけでなく、中国(北京・上海)やシンガポール、ソウルなど海外にも拠点を持ち、国内でも北海道、沖縄、富山、岡山、和歌山などに小さな拠点=「ラボ」を作り、それらをネットワークで動かしているというのです。
稲本さんは「なぜそんなに多拠点でできるのか分かっていない人もいるが、半分は研究拠点(ラボ)で、そこで生まれたものが形になる。最後にまとめ上げるのが隈事務所のやり方だ」と整理しました。
隈さんも、大きな組織は官僚化しやすく、縦割りが強くなることで全体が動かなくなる危険があると指摘します。だからこそ、半分独立しながら連携できるネットワーク型が有効であり、それは建築事務所だけでなく社会のあり方としても重要だ、という話へとつながっていきました。
次回は『日本の建築』へ
最後に稲本さんは次回予告として、2025年2月16日(30分回)で、隈さんの著書『日本の建築』を軸に、さらに丁寧に話を聞いていきたいと締めくくりました。
「自然は外にあるものではなく、素材の中にもある」。
この言葉が、石や竹の具体例とともに語られたことで、隈研吾さんの“自然”が、単なる美しい理念ではなく、現場の苦労と技術の積み重ねの上に立っている思想なのだとよく分かる回でした。